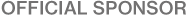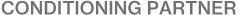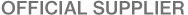第31回 全日本自転車競技選手権大会の大会要綱を以下のページに掲載いたしました。
2025-2026 シーズン JCF シクロクロスシリーズ ランキングを更新いたしました(第2戦わたり終了)。
ランキングはこちら ⇓
2025-2026 シーズン JCF シクロクロスシリーズ ランキングを更新いたしました(第2戦わたり終了)。
ランキングはこちら ⇓
「理町長杯” 東北シクロクロスシリーズ2025 第1戦 わたりラウンド」として開催された本大会は、すでに発表されている通り、2026年の「全日本自転車競技選手権大会-シクロクロス」の開催地に決定している会場で行われた。今回はプレ大会の位置づけとなったことから、東海地区や関西地区からのエントリーも見られた。
降り続く雨によりキャンバーセクションの多くは乗車率が低く、どのカテゴリでもライダーの体力を削るタフなコンディションとなった。
男子ジュニアでは、山田 駿太郎(弱虫ペダルサイクリングチーム)が蜂須賀 巧真(BUCYO COFFEE/URBAN DEER CYCLING)を振り切り、最後は独走で優勝を飾った。女子ジュニアは同時出走の女子エリートを含めても2番目でフィニッシュする快走を見せ、優勝。女子エリートは石田 唯(TRKWorks)が序盤から独走して優勝した。
男子エリートは、中盤まで織田 聖(弱虫ペダルサイクリングチーム)と沢田 時(Astemo 宇都宮ブリッツェン)のマッチアップが続いたが、織田のミスで差が広がり始める展開に。その後も織田は転倒を繰り返し、沢田に独走を許す形となり、沢田が今季初戦を優勝で飾った。
●男子エリート (3.00kmx6Laps)
1位:沢田 時 (Astemo 宇都宮ブリッツェン) 1:01:33
2位:織田 聖(弱虫ペダルサイクリングチーム)+0:57
3位:副島 達海 (TRK Works) +2:07
出走:75名、同一周回完走者:10名
●女子エリート(3.00kmx4Laps)
1位:石田 唯 (TRKWorks) 0:53:33
2位:山下 歩希 (弱虫ペダルサイクリングチーム) +2:41
3位:椿井 和佳奈 (−) +2:52
出走:12名、同一周回完走者:9名
●男子ジュニア(3.00kmx3Laps)
1位:山田 駿太郎 (弱虫ペダルサイクリングチーム) 0:32:48
2位:蜂須賀 巧真 (BUCYO COFFEE/URBAN DEER CYCLING) +0:57
3位:軽部 翔太郎 (村山産業高校) +3:17
●女子ジュニア(3.00kmx4Laps)
1位:小林 碧 (AX cyclocross team) 0:55:49
●男子U17(3.00kmx3Laps)
1位:郷津 輝 (Dream Seeker jr.Racing Team) 0:33:00
2位:村上 蕾夢 (村上兄弟) +1:32
3位:角田 直央 (Fine Nova LAB) +3:11
●男子U15(3.00kmx2Laps)
1位:村上 鳳冴 (村上兄弟) 0:24:04
●女子U17(3.00kmx2Laps)
1位:皆木 海音 (Aventura Cycling) 0:30:43
2位:阿部 怜奈 (—) +5:41
●女子U15(3.00kmx2Laps)
1位:飯島 花怜 (Team CHAINRING) 0:28:47
●男子マスターズ35(3.00kmx3Laps)
1位:畠山 和也 (ハヤサカサイクルレーシングチーム) 0:37:55
●男子マスターズ40(3.00kmx3Laps)
1位:佐藤 利英 (team chainring) 0:34:42
2位:松川 大作 (イマイシクロケッツ) +10:02
3位:半澤 和樹 (MAW) -1Lap
●男子マスターズ45(3.00kmx3Laps)
1位:太田 好政 (AX cyclocross team) 0:35:31
2位:川野 隆文 (カワノビルド) +0:08
3位:伊藤 望 (AX cyclocross team) +1:41
●男子マスターズ50(3.00kmx3Laps)
1位:生田目 修 (イナーメ信濃山形&大幸ハーネス) 0:31:03
2位:中島 由裕 (—) +1:45
3位:林 健太郎 (Team CHAINRING) +4:46
●男子マスターズ55(3.00kmx3Laps)
1位:塩見 学 (BBQ Masters) 0:35:42
2位:浅井 秀樹 (SNEL) +0:27
3位:筧 太一 (ブチョーコーヒー) +1:29
●男子マスターズ60(3.00kmx2Laps)
1位:澤田 泰征 (VOLCAオードビーBOMA) 0:23:40
2位:楠田 清徳 (MUD lovers) +3:42
3位:金子 渉 (530711) +3:58
●男子マスターズ65(3.00kmx2Laps)
1位:増田 謙一 (SHIDO -WORKS) 0:23:21
2位:江川 嘉宏 (Natural farmer) +0:58
3位:助川 修 (三菱電機(株) 郡山工場) +4:32
表記大会のエントリーリストを公開致しました。
下記大会イベントカレンダーページより、ご確認ください。
第2級公認審判員講習会トラック・ロードが長野県自転車競技連盟により2025年11月15~16日の日程で長野県松本市・スカイロードサイクリングスタジアム松本にて開催されます。
受講希望者は実施要項をご確認頂き、所定のフォームよりお申込みください。
申込期限 2025 年11 月3 日(月/祝) 23:59 迄
2025年11月4日12:00から2026年ライセンス継続申請の受付を行います。
連盟登録専用インターネットサイトから期限内に申請をお願いします。
https://entry.jcf-system.jp/jcf/login.php
【継続期間】
クレジットカード払い 2025年12月19日(金)18:00まで
コンビニ払い 2025年12月10日(水)18:00まで
加盟団体登録申請受付 2025年12月19日(金)18:00まで
加盟団体による上記承認 2025年12月25日(木)18:00まで
参考:JCF登録(https://jcf.or.jp/official/registration/)
Coupe du Japon くまもと吉無田国際 UCI-Class3 併催、ASIA MOUNTAIN BIKE SERIES FINALE STAGE が、10月18~19日 吉無田高原「緑の森」(熊本県上益城郡)にて行われた。
主な競技結果は以下の通り。
10月19日(日)
クロスカントリ・オリンピック競技
XCOコース長 4.0km
最高標高 696m
スタート標高 588m
◆Men Elite 7周回
1位 副島 達海(大阪府/TRKWorks)1:22:49.78
2位 高橋 翔(東京都/SPEED of sound)+46.78
3位 竹内 遼(静岡県/MERIDA BIKING TEAM)+1:17.33
◆Women Elite 5周回
1位 石田 唯(長野県/TRKWorks)1:15:09.97
2位 北津留 千羽(福岡県/Q-MAX)+1:31.69
3位 YAOYAO Shagne Paula(PHI/Philippine National MTB Team)+3:16.54
◆Men Junior 5周回
1位 中仙道 侑毅(埼玉県/FUKAYA RACING)1:01:56.76
2位 松山 海司(兵庫県/Sonic Racing)+2.22
3位 MANA-AY Thirdy(PHI/Go for gold philippines)+3:13.80
◆Women Junior 4周回
1位 DORMITORIO Alexandria Ayisha Aeryn(PHI/Coach D Racing Team)1:07:39.44
2位 YU Hoi Tik(HKG/Hong Kong,China)+9:45.66
◆Men Youth 4周回
1位 北津留 新羽(福岡県/Q-MAX)48:42.48
2位 浦瀧 桜雅(北海道/TEAM BG8)+5:37.40
3位 上野 倫太郎(愛媛県/SOHAYA RACING)+5:58.13
◆Women Youth 3周回
1位 有松 鈴々菜(福岡県/Q-MAX)41:28.57
2位 Aerice Dormitorio(PHI/Coach D Racing Team)+10:05.02
3位 WAN Liz(HKG/Hong Kong, China)+11:39.84
◆Men Masters 4周回
1位 吉元 健太郎(愛知県/チーム鳴木屋)57:10.92
2位 酒居 良和(広島県/マウンテン☆ポテト)+41.19
3位 坂本 泰崇(福岡県/CLICK八幡)+4:01.26
◆Men Advance 4周回
1位 積田 連(宮崎県/OLIVE)1:00:23.57
2位 安富 柊星(京都府/Un Authorized)+14.79
3位 橋本 陽介(福岡県/CLICK八幡)+23.56
◆Men Challenge 3周回
1位 下川 一翔(福岡県/久留米大学)44:02.37
2位 笠井 章生(福岡県/MASAYA RACING)+47.87
3位 松原 悠希(福岡県/TREK MINIBUS RACING)+1:31.90
10/18(土)
クロスカントリー・ショートトラック競技
XCCコース長 1.1km
◆Men Elite 6周回
1位 高橋 翔(東京都/SPEED of sound)15:09.68
2位 副島 達海(大阪府/TRKWorks)+0.68
3位 竹内 遼(静岡県/MERIDA BIKING TEAM)+2.57
■主催:吉無田MTBフェスタ実行委員会
(御船町 一般社団法人熊本県MTBリーグ オフロードバイシクル九州 よしむたMTBクラブ
一般社団法人御船町観光協会 )
■公認:UNION CYCLISTE INTERNATIONALE・公益財団法人 日本自転車競技連盟
■後援:公益財団法人日本サイクリング協会 一般社団法人熊本県自転車競技連盟 熊本県サイクリング協会
熊本県 熊本県教育委員会 御船町教育委員会 御船町商工会 一般社団法人みふね中山間地域定住支援センター
一般財団法人熊本国際観光コンベンション協会 熊本日日新聞社 NHK熊本放送局 熊本放送
熊本県民テレビ 熊本朝日放送 テレビ熊本 エフエム熊本
■開催日:2025/10/18-19
■開催地:10月18~19日 吉無田高原「緑の森」(熊本県上益城郡)
■カテゴリー:MTB XCO XCC
大会名:2025Jシリーズトライアル#03長野大会
開催日:2025/10/12
開催地:蓼科トライアルパーク(長野県茅野市豊平)
主催:JBTA 日本自転車トライアル協会
主管:茅野市自転車トライアル協会,(チーム蓼科)
トライアル国内シリーズ第3戦は、オープン2年目となる蓼科トライアルパークで行なわれた。昨年から大きな岩やコンクリート部材、丸太などの配置が変更され、新たな部材も追加されており、更にバリエーションに富むセクションが設定されていた。
午前は年少者(オレンジ、ホワイト、ブルー)と男子30歳以上のグレーが5セクション2ラップ、午後はグリーン、レッド、イエローが5セクション3ラップの設定で、各カテゴリーとも10ポイントを争う熾烈な戦いが繰り広げられた。最高獲得ポイントは午前600point/午後900pointとなっている。
2025年のJシリーズトライアルは、11月23日に椎の郷トライアルパーク(静岡県浜松市天竜区)で開催される#04静岡大会が最終戦となっている。
イエロー (15歳以上 指定男子+)
1 土屋 凌我 550point
2 横田 宏太郎 (倉敷芸術科学大学) 510p
3 濱野 伊吹 (倉敷芸術科学大学) 220p

レッド (13歳以上 男子, 15歳以上 女子)
1 増田 誠政 580p
2 内田 湊太 (IKKEI BIKE WORKS) 570p
3 柴田 泰嵩 380p

グリーン (11歳以上 男子, 12歳以上 女子)
1 藪木 佑磨 (BikenBici JAPAN) 560p
2 塚本 和志 510p
3 板谷 彼香 (RED ZONE) 390p

グレー (30歳以上 男子)
1 寺曽 秀明 (TEAM TERASO) 500p
2 田中 陽一 (MYROAD NAKANO) 490p
3 作山 幸 450p

ブルー (9-22歳 男子, 10歳以上 女子)
1 浅田 明希 530p
2 塚本 真志 470p
3 岩村 信幸 (蓼科トライアルアカデミー) 450p

ホワイト (8-16歳 男子, 8歳以上 女子)
1 山本 大地 380p
2 岩下 優月 (トライアルライダース袋井) 360p
3 佐藤 澄流 (蓼科トライアルアカデミー) 190p

オレンジ (6-12歳 男子, 6-16歳 女子)
1 浅田 竜良 600p ※フルスコア
2 田中 花穂 580p (決定戦30p)
3 山脇 明莉 580p (決定戦10p)

競技結果(リザルトPDF)
2025Jシリーズトライアル
https://jbta.jpn.org/event/2025/2025_js.htm
Jシリーズトライアル特設サイト
https://jstrial.mystrikingly.com/
副賞のグラス

なお、11月4日(火)から8日(土)にかけて、サウジアラビアの首都リヤドでアーバンサイクリング世界選手権が開催され、トライアル競技には日本から6選手が出場を予定している。
男子エリート20:土屋 凌我、横田 宏太郎
男子エリート26:濱野 伊吹
女子エリート:市川 琉那
男子ジュニア20:山下 虎威
男子ジュニア26:難波 貴彦
2025 UCI Urban Cycling World Championships
https://www.uci.org/competition-hub/2025-uci-urban-cycling-world-championships-trials/62vWqH8UXYwBkH1ROB8Zp8
公益財団法人日本自転車競技連盟(JCF)は、2025年9月23日に「ロード部会」を発足し、第1回会合を開催いたしました。
本会合では、ロード競技のさらなる発展と競技運営体制の強化を目的に、今後の方針や具体的な取り組みについて活発な意見交換が行われました。
公益財団法人日本自転車競技連盟(JCF)は、2025年9月23日「ロード部会」を発足し、第1回会合を開催いたしました。
ロード部会員
部会長
・加地 邦彦(JCF常務理事)
部会員
・中梶 秀則(JCF副会長・理事)
・飯田 太文(JCF常務理事)
・古家 由美子(JCF理事)
・大庭 伸也(JCF理事)
・別府 史之(JCF理事)
・今西 尚志
・川口 直己
・栗村 修
・樫木 祥子
・辻 啓
・松村 拓紀
基本方針
ロード部会は、以下の3本柱を基本方針として活動を進めます。
1. 問題解決型
制度・安全・普及・育成・強化など山積する課題を迅速に解決し、「2年後にはやることがなくなる状態」を目指します。
2. ドクトリン決定型
日本のロード競技が10年後にどうあるべきかを示す「Doctrine(指針)」を策定し、逆算方式で強化・普及・育成制度を再設計します。
3. 情報発信型
議論や決定事項を広く関係者・一般層に発信し、透明性と信頼性を高めます。
第1回会合の概要
・競技人口の減少傾向
・高コスト障壁への対策(重量規制・中古機材活用など)
・選手登録制度の見直し
・長期強化ビジョン(10年計画)
・多様なレース形態への対応(ヒルクライム・エンデューロ・グラベル等)
これらについて、継続的に議論・検討し、制度改革や新規施策へと発展させていくことを確認しました。
今後について
次回会合は10月末を目安に開催予定です。今後もロード部会は、課題解決と未来ビジョンの策定に向けて議論を重ね、その内容を随時発信してまいります。
公益財団法人日本自転車競技連盟
ロード部会長
加地 邦彦
バーレーンにて開幕する第3回アジアユースゲームズのお知らせです。
自転車競技は10月24日に競技開始になります。
日本チームへのご声援をよろしくお願いします。
派遣期間:2025年 10月 21日(火) ~ 11月 2日(日)
開催場所:バーレーン
<スタッフ>
清水 裕輔 (JCFロード強化コーチ)
小橋 勇利 (JCFロード強化コーチ)
<選 手>
三上 将醐 (神奈川県立横浜立野高等学校)
佐野 凌麻 (岐阜第一高等学校)
工藤 健太 (栃木県立宇都宮商業高等学校/ブラウ・ブリッツェン)
倉谷 希輝 (名古屋たちばな高等学校)
小田島 寛奈(青山学院中等部/Bellmare Women’s Racing Team)